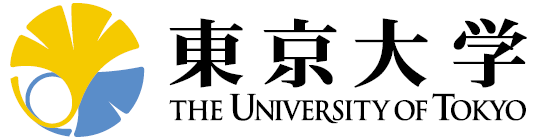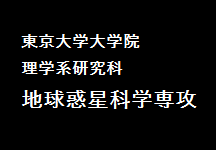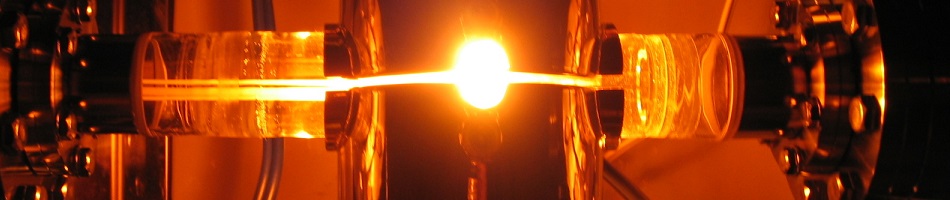
ウェブマガジン第3号
深海の謎への挑戦
日比谷 紀之 教授 (東京大学 大学院理学系研究科 地球惑星科学専攻)
1. 謎に満ちた深海 - 深層海洋大循環は「月」が駆動している!? -
光の通らない暗黒で、超高圧の過酷な世界・・・観測が非常に難しいこともあり、その実態が長くベールに包まれてきた深海は、宇宙と同じく、我々にとって謎に満ちた未知の領域です。皆さんは、深層海洋大循環といって、北大西洋北部、および、南極海で深層/底層に沈み込んだ海水が、世界中の深海を約1500年で巡り、北太平洋やインド洋などで表層に上昇して、極域へと戻っていく、あたかもベルトコンベアーのような海水循環のことを聞いたことがあると思います(図1)。この深層海洋大循環は、極域の冷たい海水を低緯度に運び、また、低緯度域の暖かい海水を極域に運ぶことで、極域(低緯度域)が極端に寒く(暑く)ならないように、いわば、エアコンの役割を果たしていると考えられています。実際、この深層海洋大循環の強弱が、氷期-間氷期スケールの気候変動を強くコントロールしてきたのではないかと考えられています。

図1: 深層海洋大循環の模式図
海水は冷やされると重くなるので、極域において海面から冷却された海水は深層/底層に沈みこんでいきます。この極域での海水の沈み込み量は、毎秒2千万トンといわれています。ベルトコンベアーが定常に動き続ける限り、この深層/底層に沈み込んだ量と同じだけの深層水が表層に戻らなければなりません。この深層水が表層に戻るのに、重要な役割を果たしているのではないかと考えられているのが、ここで取り上げる深海乱流です。
海洋は表面から太陽の日射を受けて暖められています。実は、こうして海面から加えられた熱は、海洋中の乱流の効果で次第に深い方へ伝達されていくのです。丁度、金属棒を片方から熱するとだんだんとその熱がもう片方に向かって伝わっていく「熱伝導」と同じです。極域で海面から冷却されて重くなった海水が深層/底層に沈み込むのとは全く逆のプロセスですが、乱流の働きで次第に暖められた深層水は浮力を得て、表層に上昇してきます(図2)。

図2: 深層海洋大循環の物理過程
それでは、乱流はどのようにして起されるのでしょう? 今、コーヒーにクリームと砂糖を入れます。皆さんのほとんどは、コーヒーが冷めないうちに、スプーンを使ってかき混ぜることでしょう。このようにかき混ぜ (乱流混合)をおこすには、スプーンを動かすような、何らかのエネルギーが必要です。自然界において、このエネルギーの源を追求してみると、実は、意外にも、主に「月」の引力 (潮汐力) から来ていることがわかってきたのです。
「月」による引力の作用下で、海の中には常に潮汐流が存在しています。これが海嶺や海山にぶつかると、その下流側に乱流が誘起されるのです(図3)。これは、富士山のような高い山に風があたるとその下流側に乱流が発生して、そこを通過する航空機を大きく揺らすのと同じです。

図3: 潮汐流によって海嶺や海山の下流側に誘起される乱流の模式図。
このように考えてみると、1500年スケールの深層海洋大循環は、「月」が駆動しているといえるのかもしれません。実際に、「月」の効果、つまり、潮汐力の効果を無くしてしまうと、深層水の上昇は弱まり、挙げ句の果てに、やがて、深層海洋大循環は止まってしまうことが数値実験で確かめられています。もし、地球が「月」という衛星を持っていなかったら、深層海洋大循環というエアコンも止まってしまい、人類の存在を可能にした現在の温和な地球気候は実現していなかったかもしれません。
2. 深海における乱流ホットスポットの探索
前節で述べたことからもわかるように、深層海洋大循環の時間スケールが 1500年にも及ぶことを考えると、その流れの実態を直接に深海での流速観測から捉えるのは甚だ難しく、数値シミュレーションが一番現実的な方法となります。しかしながら、数値モデルによる深層海洋大循環の強度やパターンの再現となると、モデル内で仮定する深海での乱流強度とその空間分布をしっかりと把握することが必要不可欠になってきます。
我々は、この究極的な目的に向けて、丁度、宇宙という未知の世界の探査に向けてロケットを送り込むがごとく、深海に「超深海乱流計」を送り込んで、乱流強度の空間分布の測定を行っています。
我々が現在使用している超深海乱流計は カナダ、ロックランド社製のVMP-5500と呼ばれる、世界にもまだ7台しか存在していない、非常に貴重かつ高価な精密観測機器です(図4)。VMP-5500は、水圧 約600気圧 (深度 約6000メートル)までの耐圧性を備え、秒速 約 0.6メートルで自由落下しながら(図5)、水平流速の鉛直微細構造を数ミリメートルの解像度で計測することで、乱流強度の鉛直分布を明らかにしていきます(図6)。VMP-5500は、事前に内蔵コンピュータに記憶させた深度 (6000メートル以内) に達すると、側面に取り付けたおもりを切り離し、同じく秒速 約 0.6メートルで浮上してきます(図5)。海面に浮上した後は、乱流計の先頭部に取付けてあるビーコンという測器にスイッチが入って電波が観測船に送られてくるので、この情報をもとに浮上位置を知り、回収に向かいます。水深 5000メートル程度の海では、大体、投入から5時間位で海面に浮上してきますが、その間は観測船には全く信号が届かないので、ビーコンからの電波を受信する瞬間まで、緊張から解放されることはありません。そのような、まさに、胃が痛くなるような観測を繰り返すことで推定された深海乱流の強度分布が図7なのです。

図4: 超深海乱流計VMP-5500の投入風景(小笠原諸島沖合)

図5: 超深海乱流計VMP-5500による観測の流れ

図6: 超深海乱流計 VMP-5500 により得られた観測データの一例。VMP-5500 が設定深度 (6000メートル以内) まで自由降下するまでの間、本体下部の先端部に取り付けられたシアーセンサー ( 右上) によって、水平流速の鉛直変化 du/dz (シアー) が数ミリメートルの解像度で測定される。この流速の微細構造から乱流エネルギー散逸率を計算することで、深海における乱流強度を求める。
3. 深層海洋大循環の駆動メカニズムへの挑戦!
図7を見てもわかるように、深海乱流の強い場所 (乱流ホットスポット)は、顕著な海嶺や海山の存在する位置とほぼ一致しています。しかしながら、高い海山と潮汐流があれば乱流が生まれるのかというと、そうとも限りません。例えば、アリューシャン海嶺では、強い潮汐流が高い海山にぶつかっているのに、乱流の強い領域はアリューシャン海嶺から広がっていません。実は、理論的な解析から、月の引力から与えられた潮汐流は、緯度30˚よりも低緯度側にある海嶺/海山にぶつかると、強い乱流を引き起こすものの、緯度30˚より高緯度にある海嶺/海山にぶつかっても、乱流を引き起こさないことが明らかにされています。図7に示す乱流強度の観測結果は、まさにその理論的な予測と合致しています。

図7: 様々な海域で行った乱流観測の結果を総合することにより推定した深海乱流の全球的な強度分布
ただ、こうして観測されたホットスポットにおける乱流強度を足し合わせても、毎秒2千万トンに及ぶ深層水を表層に引き上げるのに必要な乱流強度の約1/5程度にしかなりません。まだ世界の海洋中のどこかに乱流ホットスポットが見つからずに存在しているのでしょうか?それとも、乱流以外に、深層水を表層にまで引き上げる何らかのメカニズムが存在しているのでしょうか?
皆さん、深層海洋大循環の駆動のメカニズムの解明を目指して、我々と一緒に、この海洋物理学に残された最大の謎解きに挑戦してみませんか?